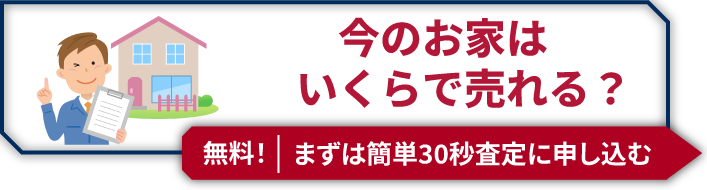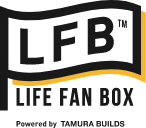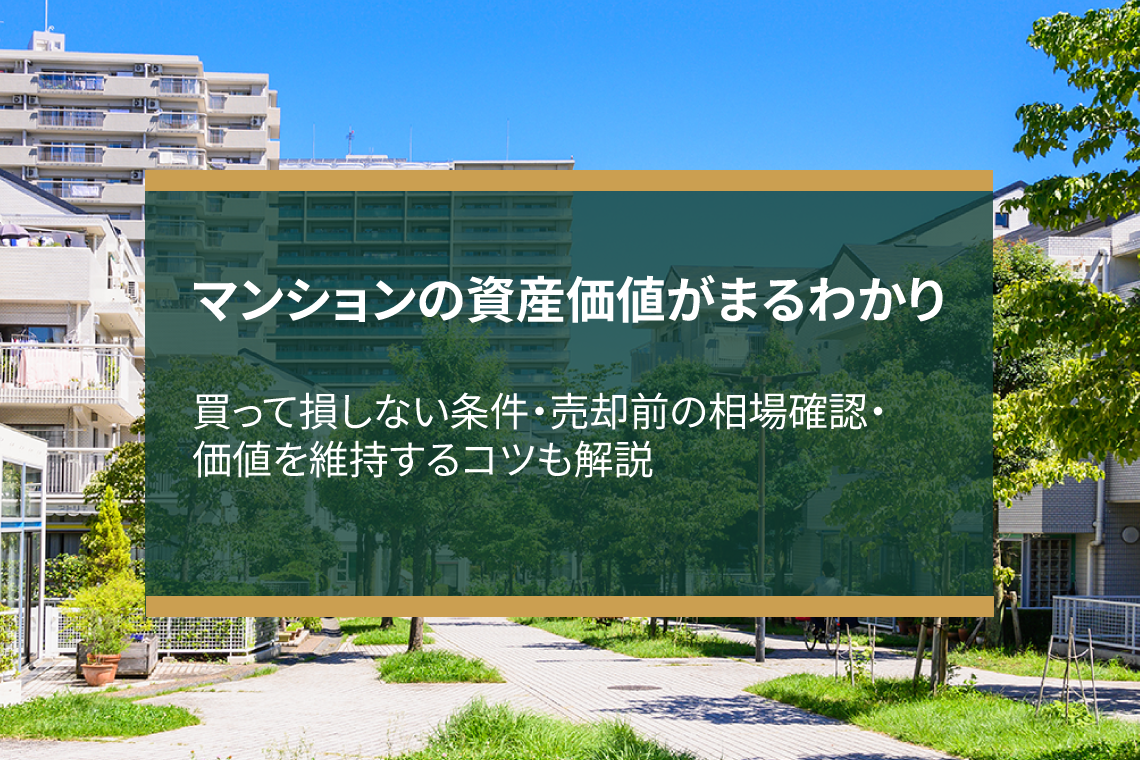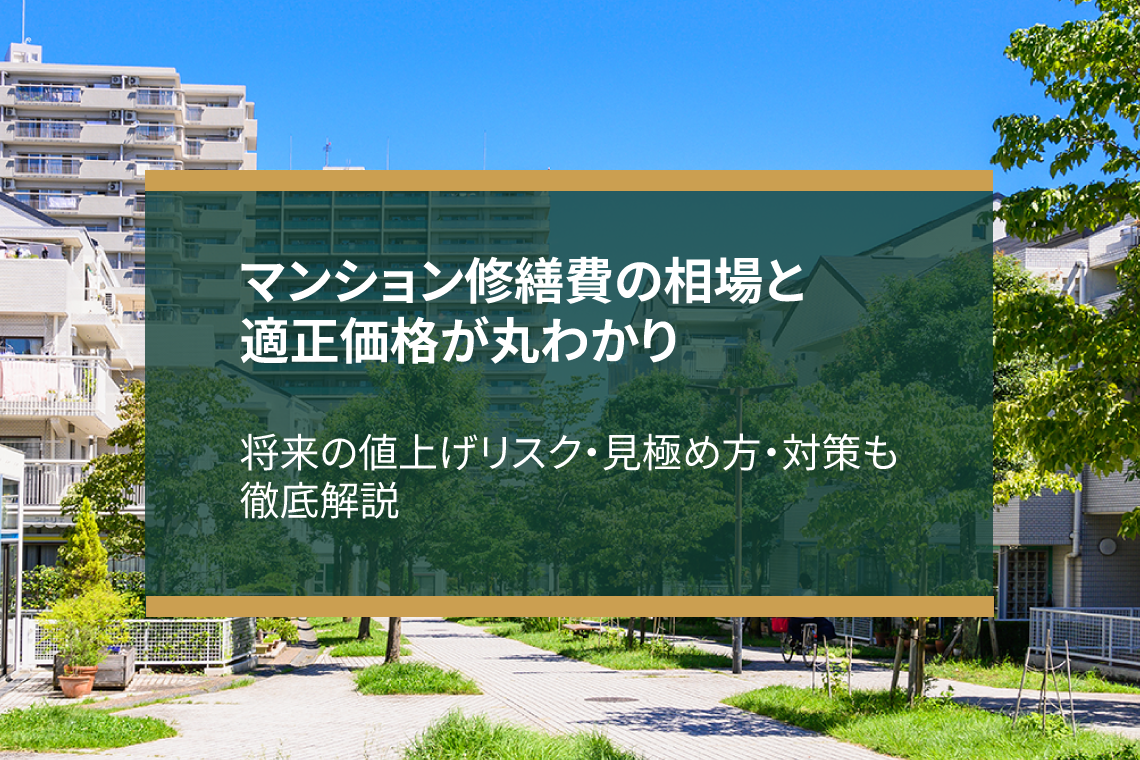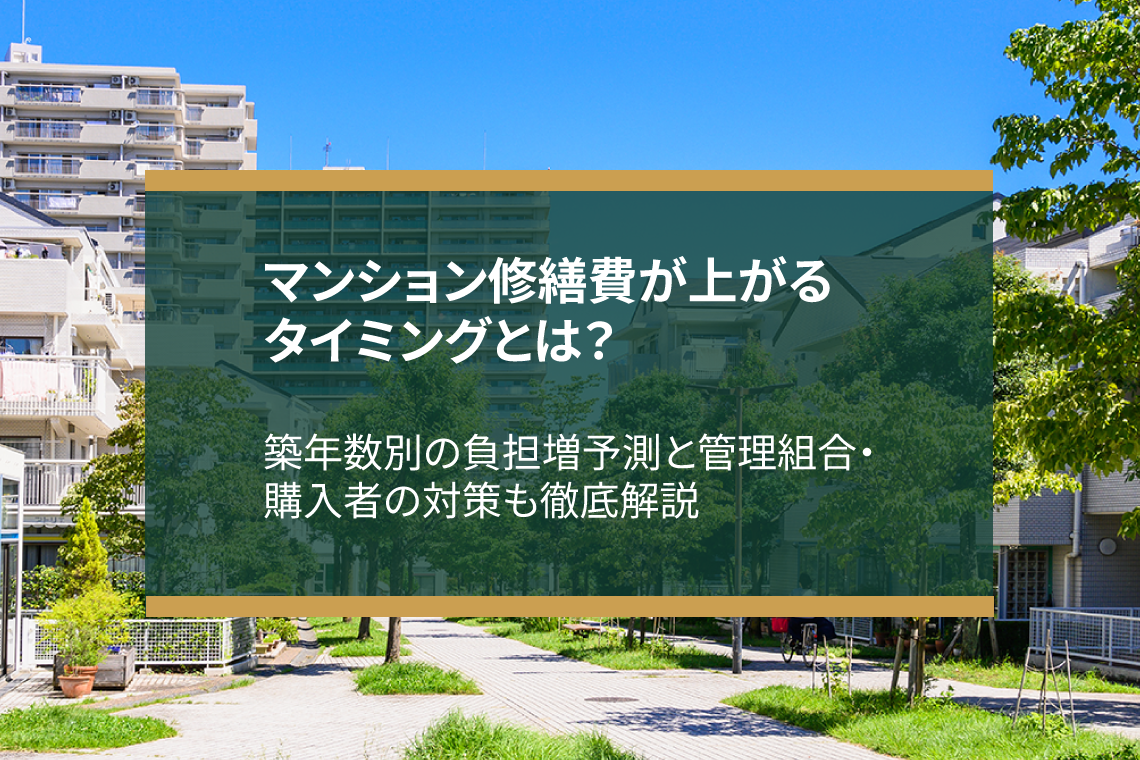NEWS
お知らせ
- BLOG
- 2025.8.7
「専有面積とは?バルコニーは含まれる?中古マンション・賃貸の疑問を初心者から投資家まで徹底解説」
マンションの購入や賃貸を検討する際に、「専有面積(せんゆうめんせき)」という言葉を必ず目にします。しかし、「専有面積にバルコニーは含まれるの?」「実際に使える面積ってどうやって考えたらいい?」「登記簿の面積と違うのはなぜ?」など、疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
特に中古マンションを検討している方や、初めてマンション購入をする20代~40代の初心者の方、投資目的の方、賃貸物件を探している方と、疑問の内容もさまざまです。
本記事では、専有面積の基本的な意味から、バルコニーや共用部分の扱い、計測方法の違い、築年数による表示の差、投資用物件の見方や賃貸での活用法まで、幅広い角度で詳しく解説します。
専有面積の疑問を解消し、安心して物件選びができるよう、わかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
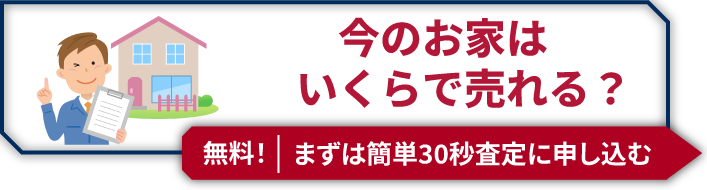
1. 専有面積とは?基本の意味と定義
専有面積とは、マンションの一戸ごとに「所有者が専用に使える部分の面積」を指します。
具体的には、居室やキッチン、バスルーム、トイレ、収納スペースなど、その住戸の中で自由に使える室内の床面積のことです。
法律上の定義は、建築基準法や区分所有法などに基づきますが、専有面積の測り方には「壁芯(へきしん)面積」と「内法(うちのり)面積」の2種類があり、どちらで計測されているかによって数値が異なります。
・壁芯面積:壁の中心線を基準にして計測
・内法面積:壁の内側の線(壁の内側の面)を基準にして計測
多くのマンションでは壁芯面積を専有面積としている場合が多いですが、中古マンションや築年数の古い物件では内法面積を使うこともあります。
この違いにより、同じ部屋でも専有面積の数値が異なることがあるので注意が必要です。
2. バルコニーは専有面積に含まれる?
マンションのパンフレットや契約書でよく質問されるのが「バルコニーは専有面積に含まれるのか?」という点です。
一般的には、バルコニーは「専用使用部分」ではありますが「専有部分」ではなく、共用部分に分類されます。
そのため、多くの場合、バルコニーの面積は専有面積に含まれません。
ただし、管理規約や登記の内容によっては、バルコニーの一部が専有面積に含まれていることもあります。
また、広告や重要事項説明書では「専有面積+バルコニー面積」という形で分けて表示されているケースもあります。
まとめると
・バルコニーは基本的に専有面積に含まれないが、専用使用権がある
・面積表示は「専有面積」と「バルコニー面積」を分けて記載することが多い
・物件ごとに異なるため契約書や管理規約の確認が必要
バルコニー面積は固定資産税の算定には含まれないことが一般的ですが、住宅ローン控除の対象となるかは物件ごとに異なるため、専門家への相談をおすすめします。
3. 壁芯面積と内法面積の違いを解説
専有面積を測る基準として「壁芯面積」と「内法面積」がありますが、違いを知っておくことは物件選びの際に重要です。
3-1. 壁芯面積(へきしんめんせき)とは?
壁の中心線を基準に、部屋の外壁と隣戸との壁の中心を囲んだ面積です。
この測り方は壁の厚みの半分も含むため、内法面積よりも広くなる傾向があります。
3-2. 内法面積(うちのりめんせき)とは?
壁の内側の線で囲まれた面積で、実際に壁の内側で使える空間の広さに近いとされています。
3-3. どちらが多い?
日本のマンションでは法律上、壁芯面積を専有面積として扱うことが多いですが、築年数の古い物件や一部の不動産広告では内法面積が使われていることがあります。
3-4. 実際の差は?
壁の厚さや柱の大きさによりますが、壁芯面積のほうが内法面積より5~10%ほど広くなるケースが多いです。
この違いにより、例えば「専有面積70㎡」と聞いても、実際に住めるスペースは若干狭い可能性があることを理解しておきましょう。
4. 専有面積と実際の生活スペースの違い
専有面積は法律上の計測方法に基づく「数字」であり、壁や柱、配管スペースも含むため、必ずしも「実際に家具を置いて生活できるスペース」とイコールではありません。
たとえば、壁の厚み分や配管の空間は使えませんし、梁(はり)が出ている場合は家具の設置が制限されることもあります。
また、間取りの形状や柱の位置によっては、使い勝手が変わることもあります。
このため、購入前には必ず現地の内見で、間取り図だけでなく「実際の空間の広さ」や「家具の配置イメージ」を確認することが大切です。
5. 登記簿の面積と専有面積が違う理由
登記簿に記載されている面積は、法務局に登録された「建物の床面積」であり、原則として壁芯面積が基準です。
一方、不動産広告や重要事項説明書に記載される専有面積は、内法面積が使われることもあり、場合によっては差異が生じます。
また、築年数が古いマンションでは、当時の計測基準が異なるため登記簿と現状の専有面積に差が出るケースもあります。
リフォームや増築で専有部分が変わった場合、登記簿の面積は変更登記を行わない限り更新されません。
これらの理由から、登記簿の面積と広告上の専有面積に違いが出ることがあるのです。
6. バルコニーや共用部分の面積の記載場所は?
バルコニーや廊下、エントランスなどの共用部分の面積は専有面積に含まれませんが、建物全体の管理や維持費の算定に関わります。
・バルコニーの面積:登記簿の「附属建物」として別途記載されている場合が多い
・共用部分の面積:マンション管理規約や重要事項説明書に記載がある
管理費や修繕積立金の計算は、専有面積に応じた負担割合を基本にしつつ、共用部分の維持管理費を分担する仕組みです。
7. 30㎡の広さってどれくらい?専有面積のイメージ例
30㎡は約9坪で、一般的なワンルームや1Kの賃貸物件の広さに相当します。
・例えば、約6帖の居室+キッチンスペース+バス・トイレが含まれることが多いです。
・一人暮らしの方が生活するには十分な広さですが、家具の配置や収納スペースの確保がポイントになります。
間取り図の見方や実際の広さイメージを掴むために、下記のような具体例も参考になります。
・シングルベッド(約100×200cm)が置けるか
・ダイニングテーブルの設置スペース
・クローゼットや収納家具の配置
こうした実生活のイメージを持つことで、専有面積が数字だけでなく「使える広さ」として理解できます。
8. 中古マンションの築年数で面積表示に差が出る理由
築年数が古いマンションでは、計測方法や表示方法が現行の基準とは異なる場合があります。
・昭和期のマンションは内法面積を使うケースが多い
・平成以降は壁芯面積が一般的
・リフォームや間取り変更で専有面積が変わっている可能性も
そのため、新築と中古で同じ専有面積表示でも、実際の使える空間や計測基準が違い、比較すると違和感を感じることもあります。
9. 投資用マンションの面積の見方と利回り計算のポイント
投資用マンションの場合、専有面積は賃料の設定や利回り計算に大きく影響します。
・バルコニーの面積が含まれているかどうかで、実際の収益性に誤差が出ることもある
・登記簿と広告の専有面積の差異は必ず確認し、収益計算に反映する
・専有面積の大きさにより、管理費や修繕積立金の負担も変わるため、利回り計算時に注意
投資判断の際は、専有面積だけでなく、物件の築年数、立地、管理状況も総合的にチェックすることが大切です。
10. 賃貸物件での専有面積の活用方法
賃貸物件探しでは、専有面積が物件選びの重要な指標になります。
・同じ間取りでも専有面積が異なることがあるため、面積だけで比較せず、実際の間取り図や現地内見で生活イメージを掴む
・バルコニーがあるかどうか、収納スペースの広さもチェックポイント
・30㎡前後の物件の特徴を理解し、自分の生活スタイルに合った広さを選ぶ
複数物件を比較検討する際、専有面積を基準にしつつ、生活の利便性や設備も併せて検討しましょう。
11. 専有面積に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 専有面積と建物面積はどう違う?
専有面積は住戸単位の「専用に使える部分の面積」、建物面積は建物全体の床面積です。
Q2. バルコニーの面積は固定資産税に影響する?
一般的にバルコニーは共用部分か附属建物として扱われ、専有面積には含まれないため、固定資産税の計算には反映されにくいです。
Q3. 壁芯面積と内法面積、どちらを優先すべき?
新築や広告では壁芯面積が一般的ですが、実際の生活空間に近いのは内法面積です。購入検討時は両方の数値を確認しましょう。
Q4. バルコニー面積はどこで確認できる?
登記簿の附属建物部分や管理規約、重要事項説明書に記載があります。
12. 専有面積に関する無料相談のご案内
専有面積の計算方法や表示の違い、物件ごとの面積確認、バルコニー面積の扱いなど、わかりにくい点はぜひ当社の無料相談をご利用ください。
経験豊富な不動産スタッフが、お客様の疑問や不安を丁寧に解消し、納得のいく物件選びをサポートします。
無料相談はオンライン・対面どちらも対応可能。お気軽にお問い合わせください。